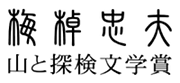著者 荻田 泰永(おぎた やすなが)
北極冒険家
1977年神奈川県出身
2017年度植村直己冒険賞
2018年日本人初、南極点へ徒歩による無補給・単独踏破に成功
選考委員会の講評
「第9回梅棹忠夫・山と探検文学賞」の選考委員会は2月20日、山と溪谷社会議室において行なわれました(体調不良で1名欠席)。今回、選考対象44作品から、最終選考に残ったのは以下の5作品です。
- 三浦英之著『牙 アフリカゾウの「密猟組織」を追って』(小学館)
- 服部英二著『転生する文明』(藤原書店)
- 松本紀生著『極北のひかり』(クレヴィス)
- 北澤豊雄著『ダリエン地峡決死行』(産業編集センター)
- 荻田泰永著『考える脚』(KADOKAWA)
考えさせられる『牙』、知的刺激に満ちた『転生する文明』、スペクタルな『極北のひかり』、無鉄砲な『ダリエン地峡決死行』、冒険心に富んでいる『考える脚』。今回、最終選考に残った5作品はどれも個性的な味わいがあります。また、濃淡はありますが、どの作品も行為と思索、過去と現在が緊密に結びつきながら、日常と非日常的な感覚、認識、さらには変化しながら深いところでつながっている「世界」を、思いがけない仕方で問いかけてきます。
そこには、従来型の冒険・探検譚にありがちな、目の前に立ちはだかる対象にしゃにむに立ち向かう直截性はありません。長い年月と真摯な活動を介して獲得された「確実な事実認識」を基に、「トリックスター」を思わせる自由な発想と直感、対象としなやかに関わる成熟した行為者の世界が広がっています。それが作品の「個性」の源泉なのです。
今回の選考会議では、この「個性」を巡って、選考委員各位の専門性、活動領域によって評価が分かれました。そのなかで、『考える脚』と『転生する文明』の2作品に絞られましたが、4対1で『考える脚』に決定しました。
この4年間の授賞作品は、本格的な山岳・探検譚とは趣の異なる作品が選ばれていましたが、『考える脚』は、20年間に渡って極北に関わり続けてきた荻田氏の「冒険哲学」が結実した作品です。北極探検家、荻田泰永氏の受賞を、選考委員一同心から嬉しく思います。
『牙 アフリカゾウの「密猟組織」を追って』の著者は新聞記者ですが、大学院で人間環境学を専攻、「ゾウと人間のかかわり、この巨大動物の終焉の可能性を見極めたい」という思いがありました。2014年、アフリカ特派員として赴任すると、象牙の密売組織の暗部に迫ります。その過程で、アフリカ諸国を覆う様々な不条理、象牙の巨大市場を操る中国、伝統文化の護持という綺麗ごとに終始する日本。それらが一本の糸でつながっている「闇」を白日の下にさらします。著者は「…そう遠くない未来にほぼ100%の確率で、(アフリカゾウ)は地球上から消滅する」と断言します。生きているように4本の足を折って座っているが、顔を切り落とされた巨ゾウの写真は衝撃的で、本書のすべてを物語っています。重いテーマですが、著者の行動力と取材力に裏打ちされた文章力、表現力で読むものを引き込みます。ただ、現地支局員、日本人獣医と著者のかかわりを積極的に描けば、報道記事とは一味異なる作品に仕上がったのではないか。また、著者の正義感、使命感、職業意識が、人間の業の発露でもある「探検」と微妙にずれている、という指摘もあり、受賞を逃しました。
『転生する文明』は難解ですが、刺激的でスケールの大きな作品です。著者はユネスコに勤務し、「世界遺産」等の仕掛人であり、シルクロード総合調査等の中心メンバーとして活躍した比較文明学の泰斗です。その「特恵的」な役割を活用しながら、100カ国余の地域を踏査しました。「自分の足で歩き、自分の頭で考えよ」という、梅棹忠夫の学問に向かう姿勢を彷彿とさせます。本書はその調査、研究の積み重ねと、類まれな直観力とが交錯した成果です。著者は、古代人は大河を行き来し、さらに海流の発見で、隔絶された地域間との交流が活発だったと指摘します。「文明は旅をしながら」「転生と変貌を繰り返し」「通底=深みにおける出会い」があったのです。その奇跡的な通底、例えば、ボロブドゥ-ル・アンコール・セイロン・ジャワ・長安・奈良を結ぶ思想、マヤ文明とインドネシアの山岳信仰との関係性等々、意表をつく仮説が次々に検証されます。本書は文明史を超えた文明誌であると、高い評価がありました。しかし、一定の基礎知識、興味がなければ通読は難しく、論述の適否も判定できない、読み物として文章の魅力に欠ける等の意見が強く、惜しくも授賞を見送りました。
『極北のひかり』は、写真家である著者が、20余年に渡って撮り続けてきたアラスカの大自然、そこで営まれる生物と、それらと真摯に対峙しつづけてきた著者自身の生き様を著したノンフィクションです。併せて、同書に収められたアラスカの「四季」を切り取った写真から、著者の被写体に向かう執念とこだわり、アラスカという大地に抱く畏敬と憧憬が伝わってきます。漠然とした気持ちで京都の大学に入学した著者は、写真家の星野道夫氏の著書『アラスカ 光と風』と出会い、「アラスカを撮る写真家になる」ために突き進んでいきます。アラスカ大学に再入学し「アラスカ」に馴染みなながら、卒業後は、1年のうちの半年を極北の大地で、一人でキャンプ生活をしながら撮影に取り組みます。著者にとって「アラスカ」は、もはや「日常」なのです。とはいえ、「日常」に潜む「慣れ」を拒絶します。その姿勢が見事なまでに貫かれた良心的な作品です。しかし、第7回梅棹賞を受賞した大竹英洋氏の『そして、ぼくは旅に出た。』と同系統の作品であり、その構成力、文章の力強さにおいて、及ばないという評価で、授賞には及びませんでした。
『ダリエン地峡決死行』は、わずか数日の冒険ですが、スリリングで痛快、等身代の作品です。2011年、33才の著者はコロンビア大学の語学コースに通っていましたが、アルバイト先の日本人社長から「ダリエン地峡」を紹介されます。コロンビアとパナマとの国境地帯ですが、人を喰う木の伝説もあるほどの、鬱蒼としたジャングルです。ここを通るのは現地の先住民の他は、難民か、犯罪者か、コカインの運び屋、売春婦、逃亡者だけです。著者の冒険魂に火がつきました。2011年9月、第1回目は、出発した日に政府軍と出会い、引き止められます。いったん帰国し、2013年に再び決行します。この時は、クナ族の部落に1週間ほど滞在、クナ族の青年、校長らに同行し、目的を果たします。本書は好奇心旺盛、物おじせず、余計な詮索をしない、著者の人柄が滲みでた好著です。クナ族との交流、彼らの習俗、風習が興味深く描かれています。しかし、異なる場と時間の話が脈絡なく繰り返され、読む人は混乱します。ウイキペディアのような紹介文は退屈です。読ませようとようする構成力を意識すれば、さらに面白くなったはずです。受賞には届きませんでした。
『考える脚』には、北極点無補給単独徒歩(2014年)、カナダ〜グリーンランド単独行(2016年)、南極点無補給単独徒歩(2017年〜18年)の三篇が収められています。それぞれが1冊の作品になるほどの、冒険探検界の偉業です。本書を手にするまで、消化不良のままの、平板な冒険譚になっていないかとの危惧がありました。見事に裏切られました。本書は、20年間の極北での活動と体験に裏打ちされた確信を基底に、自然とは何か、自分とは何かを問いつづけた冒険者が到達した「思索」の集大成なのです。ソリを使った単独行、深く自然の中を旅しているときに感じる「自由」、努力でなく憧れの力が旅の原動力となる、危険とは、困難とは……、冒険を介した思索の深まりが、リアルな言葉で語られています。著者は犬ゾリを使わず、小型のソリを一人で曳いて、ローカルな支援者と密接につながり、可能な限り経費を切り詰めています。あの不世出の冒険家植村直己氏が追い求めたであろう冒険スタイルを創り上げ、新たな地平を切り開いたと言ってよいでしょう。明瞭で無駄のない文体、構成力も申し分なく、第9回梅棹賞に決定しました。
信濃毎日新聞記事

2011-2025 © 「梅棹忠夫・山と探検文学賞」委員会