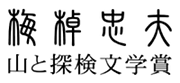著者 大竹英洋(おおたけ ひでひろ)
写真家
1975年京都府舞鶴市生まれ
一橋大学社会学部卒業
1999年よりアメリカとカナダの国境付近から北極圏にかけて広がる北米の湖水地方「ノースウッズ」をフィールドに、野生動物や自然と人間との関わりを追って撮影を続けている。
選考委員会の講評
「第7回梅棹忠夫・山と探検文学賞」の選考委員会は3月19日、山と溪谷社会議室において、選考委員5人全員が出席して行なわれました。今回、選考対象50作品から、最終選考に残ったのは以下の5作品です。
- 廣川まさき著『ビックショット・オーロラ』(小学館)
- 吉田勝次著『洞窟バカ すきあらば、前人未到の洞窟探検』(扶桑社)
- 上原善広著『カナダ 歴史街道をゆく』(文藝春秋)
- 佐々木芽生著『おクジラさま ふたつの正義の物語』(集英社)
- 大竹英洋著『そして、ぼくは旅に出た。はじまりの森ノースウッズ』(あすなろ書房)
今回の選考会は最初から波乱含みでした。一つに、選考委員2名が入れ替わり、新しい風が吹いたことです。また、7年という歳月を経て、選考に関わってこられた委員にも、作品としての完成度をこれまで以上に求め、必ずしも毎回「受賞作」を選出することはないという機運が醸成されていたことです。そうした中で毎回議論になるのが、読者にある程度の専門的素養が必要とされる研究書的作品、論文調の文体、このような一群の作品が、果たして「文学」賞に相応しいのかということです。
そこで今回、最終選考作品の選定に際し、梅棹忠夫氏がよく口にされた「おもろいな」について考えてみました。多様な視点に注意を払い、好奇心の赴くままに対象に接近し、つかみ取る。混然とした中に光るものがあり、それが人を惹きつけ知的興味を刺激する。そのような「おもろさ」を、もう一つの選考基準にしたのです。当然、最終選考に残った作品に、違和感を覚えた選考委員がおられました。今回の選考会に3時間も要した「波乱」の一因になったようです。
弊賞は「梅棹忠夫」=アカデミック的手法と内容、「山と探検」=野外での創造的な行動とエンターテイメント性、「文学性」=読み物としての完成度、この3要素が均衡した作品との出会いを求め続けていきます。
『洞窟バカ』は、まさに「おもろい」を巡って議論がかわされました。仕事と両立させながら国内外の洞窟探検をつづけるエネルギーと情熱、それが作品の随所からほとばしり、ワクワクしながら次のページをめくりたくなります。洞窟という異界に広がる風景を切り取った写真も迫力があり、圧倒されます。しかも、冒険と探検の違いを分析し、自分を洞窟探検家と位置づける冷静さを持ち合わせています。しかし、先ず問題にされたのが文体です。「オレ」を主語に「悪ガキ」を装うような言いまわしは、一見、著者の天衣無縫な個性を想像させ、本書の特徴を際立てさせているようにみえるのですが、粗野な表現がアマチュアの自己満足という印象を与え、却って感動を削いでしまうのです。文体はこのままでも、洞窟探検の醍醐味を的確に伝える、著者ならではの含蓄のある表現、語彙を探しあてた時、これまでとは違う読者層を獲得するはずです。さらに、ビジネス書、道徳教科書的な結論も、折角の探検譚に水を差しています。「おもろい」には、あと一皮剥く作業が欲しかったのです。
『カナダ 歴史街道をゆく』は、2015年と16年、それぞれ3カ月に渡って、プリンスエドワード島からバンクーバーまで横断、さらに北極海に面したタクトヤクタックまでの、およそ1万キロに及ぶ旅の記録です。その20年前、23歳の著者は、ハンティング用カートでユーコン準州からブリティッシュ・コロンビア州まで、3カ月かけて縦断した経験があります。今回は自転車、バス、レンタカー、鉄道など様々な移動手段を使って、カナダ建国150年の時空間を自由気ままに行き交っています。決して危険をともなう冒険ではないのですが、広い意味での知的な探検だといえます。ところが、1万キロの旅を過不足なくつづることが目的になっているのでしょうか、折角、魅力的な人たちと出会っても、歴史に埋もれかかった先住民族とヨーロッパからの開拓者との軋轢、ロシア、中国、日本からの移民の光と影、第二次大戦時の日系人強制収容所の話題なども、もう一つ胸に響いてこないのです。余りに淡白で、著者が本作品に込めたはずの「叫び」が聞こえてこなかったのです。
『ビッグショット・オーロラ』は世界的地球物理学者で、オーロラ研究の第一人者であるアラスカ大学名誉教授、赤祖父俊一(1930年12月~、取材当時85才)との対話を介して、誰にでも分りやすく科学の目線でオーロラの謎に迫った、著者ならではの作品です。歯切れの良い熟達した文章も魅力的です。著者は科学者ではありません。アラスカという大地と、そこで生きる人たちに恋をして、自らユーコン河1500キロを単独カヌーで下った冒険者であり、ノンフィクションライターなのです。「オーロラは伝説であり、探検であり、冒険であり、歴史であり、科学であり、そして多くの人の人生を巻き込んだヒューマンドラマだ」と言うように、著者の好奇心が向かう先は多様で「おもろい」のです。しかし、著者・アカソフ先生・アラスカの大地と自然との間の均衡と緊張を掘り下げていたら、たまたま知り合ったアカソフ先生から、オーロラの不思議を聞きだし、素人ながら上手くまとめました、という臭いは消えていたはずです。受賞にあと一歩及びませんでした。
『おクジラさま』の著者は、ニューヨークに拠点を置く映画監督で、09年に公開された「ザ・コーヴ」を見て衝撃を受けます。「(反捕鯨)が絶対の正義であり、(太地町の)漁師たちが悪であるという」独善的な意図で撮られ、「ドキュメンタリー作家としての倫理の許容範囲を超えている」と感じたからです。が、同年のアカデミー賞を受賞、太地町の人たちの声はかき消されていきます。この理不尽な状況を前に、著者は「ザ・コーヴ」に対峙するドキュメンタリー映画の制作を決意します。大地町とアメリカ市民社会の両方にキッチリと軸足を置き、容認派と反捕鯨派が掲げる「正義」、その基底にある「文化」に、知力と体力の限りを使って忍耐強く立ち向かいます。明確な問題意識、民族学の相対主義に通じる手法、冷静かつ説得力のある文章。本書は歴史に残る可能性を予感させます。ただ、政治、文化、民族、歴史、思想、産業構造などが複雑に絡み合い、グレーゾーンの幅が広い「おクジラさま」を、敢えて、「ふたつの正義」に収斂させない仕方もあったのではないでしょうか。激論の末に受賞を逃しました。
『そして、ぼくは旅に出た。』は、アメリカ北部に広がる森と湖の自然豊かな「ノースウッズ」に3カ月ほど滞在した時の生活譜です。自然写真家志望の著者は、『ナショナル・ジオグラフィック』誌などで活躍している自然写真家ジム・ブランデンバーグの作品に触発され、1999年5月、24歳の時にジムのもとへ旅立ちます。8日間のシーカヤックの旅、30日余の大自然に囲まれた生活は、危険のともなう冒険でも、未知との遭遇に向かう探検でもありません。しかし、自然写真家への道を歩む決意を固めた旅であり、人と動物たちが等価に生きている悠々とした大自然の姿、それと表裏をなす観測史上最大級の嵐を体験し、自然の凶暴さも知る旅だったのです。多くの出会い、経験を砂にしみこむように取り入れる素直でしなやかな感性と、情景が浮かび上がるような静謐で新鮮な文体が調和しています。過去・現在・未来をフラッシュバックする構成も効果的です。ただ、本文をもっと削ぎ落し、その分、著者の最近の写真を載せることで、より生新さが醸し出されたのではないでしょうか。僅差での受賞でした。
信濃毎日新聞記事
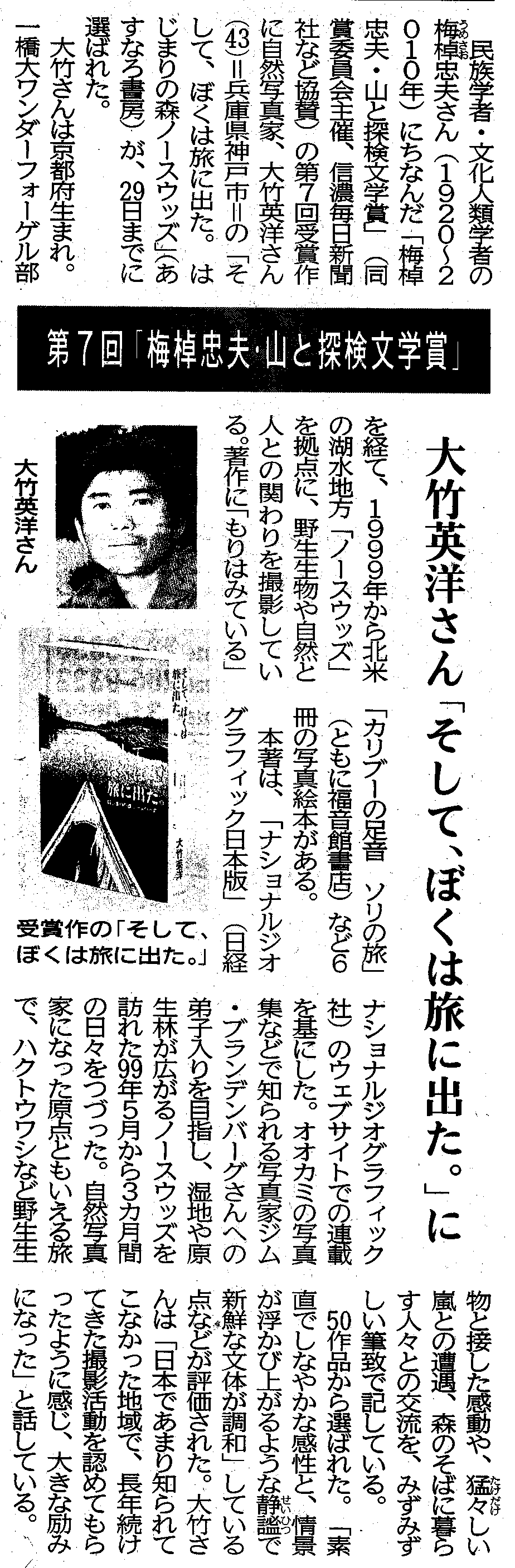
2011-2026 © 「梅棹忠夫・山と探検文学賞」委員会