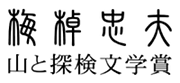著者 佐藤優(さとう まさる)
元外交官。作家
1960年東京都出身
同志社大学大学院修了
在ロシア日本国大使館三等書記官、外務省国際情報局分析第一課主任分析官、外務省大臣官房総務課課長補佐を歴任。
選考委員会の講評
「第8回梅棹忠夫・山と探検文学賞」の選考委員会は3月22日、山と溪谷社会議室において、選考委員5人全員が出席して行なわれました。最終選考に残ったのは以下の4作品です。
- 小松 貴著『昆虫学者はやめられない 裏山の奇人、徘徊の記』(新潮社)
- 国分 拓著『ノモレ』(新潮社)
- 服部正法著『ジハード大陸 「テロ最前線」のアフリカを行く』(白水社)
- 佐藤 優著『十五の夏』(幻冬舎)
今回、最終選考に残った4作品は、山岳、極地、海洋など、典型的なフィールドに立ち向かう探検・冒険譚とは肌合いが違います。仕事を介して出会った事象、少年期からの体験をじっくりと発酵させ、個性豊かな表現様式で仕上げています。読み比べるにつれ、現代社会に蔓延する種々雑多な情報に影響されたステレオタイプな「知識」の脆弱性に気づかされます。選考委員一人ひとりが、評価基準の内実、妥当性を問われ続け、これまでにない「疲労」を憶える選考会議となりました。
情報に接し、収集し、整理し、判断し、公表する…、一連の作業には、意識的にせよ、無意識にせよ常になんらかの偏りがあります。誠実な研究者、ジャーナリストは現場に足を運び、データを積み重ね、事象の客体化に努めます。『ジハード大陸』、『昆虫学者は止められない』はその好例です。逆に、ノンフィクションとフィクションの境界を意識的に混然とさせ、物語化することで真実に迫ろうとする手法もあります。『ノモレ』、『十五の夏』がそうです。
今回の選考会では、「ドキュメンタリー」の既成概念が破られ、その奥深さ、無限の可能性を認識させられました。『十五の夏』と『ノモレ』が残り、1時間を超える議論を経て3対2で『十五の夏』に決まりました。しかし、選考委員は、どちらに決まっても納得できると評していた、という意味で全会一致の授賞といえます。
ところで、歴代の弊賞授賞者の活躍を知るのは嬉しい限りです。大竹英洋氏が「日経ナショナル・ジオグラフィック写真賞2018」のネイチャー部門で最優秀賞を受賞しました。角幡唯介氏は「第45回大佛次郎賞」を受賞し、中村保氏、高野秀行氏、服部文祥氏も話題になる本を出しています。
『昆虫学者はやめられない』は、旺盛な行動力、ち密で既成概念にとらわれない観察力、知識力、それらに裏打ちされた軽妙洒脱な文章は相変わらずです。読者は「小松ワールド」に引き込まれていきます。
カラスの執念深さ、ホソミオツネントンボ、ハナカマキリなどの擬態、アリとアブラムシとの共生、在来種と外来種を巡る深淵な考察、一筋縄ではいかない新種発見(ちなみに著者が発見したハネカクシが、2011年に新種と認定された)の現場等々、昆虫の意外な生態、昆虫学の現況が次々に解き明かされます。豊富なカラー写真も効果的で、読者の理解を助けてくれます。何の変哲もない裏山が、昆虫たちの果てない生命圏へと姿を変え、私たちに取り付いた昆虫への常識がゆすぶられるのです。
本書は、それほど魅力的なのですが、ややもすると軽口めいた印象を与えかねない文体、アニメ論、テレビドラマの「水戸黄門」などの過剰な蘊蓄が気になりました。その分、昆虫採集にともなう自然相手の困難さ、探検活動に触れてほしかったという指摘がありました。授賞を逃しました。
『ジハード大陸』は、真摯なジャーナリストによる渾身の一作です。著者は、2012年から4年間、新聞社のヨハネスブルグ支局長として、アフリカ49か国を担当しました。赴任した4日後、西アフリカのマリでクーデターが起こりました。ところが、わずか3カ月の間に、反政府軍が支配した北部のほぼ全域を、外国人を寄せ付けないジハーディストが占拠したのです。「…北部の実態をこの目で見たい。記者として…強い思いが募」ります。誘拐の恐怖を感じながら、通訳兼助手と向かった地域は、兵士と警察官が目立つ荒れた“まち”でした。
事実を追い求めケニア、ソマリア、南アフリカ、エチオピア、マリ、ニジェール、ナイジェリア、南スーダン、チャド、コンゴ…へと飛び回ります。どこも、政府・反政府、民族・部族、宗教、大国のエゴ…などが複雑に絡み合う紛争、テロ、むき出しの暴力が支配する荒涼たる地域で、コンゴではエボラ出血熱の蔓延が追い打ちをかけました。
宗教思想を基底にしたアフリカの混乱情況に眼を配り、アフリカの今を的確に捉えた好著です。しかし、本質的には新聞記事の延長的なルポルタージュです。そのため客観性を強く意識した文体となり、残念ながら読み物としての面白さを削いでしまったように思います。授賞に至りませんでした。
『ノモレ』は一筋縄ではいかない特異な作品です。否応なく文明社会と接触せざるを得ない先住民の戸惑いと苛立ち、観光事業を優先させ、場当たり的な対応に終始する政府、先住民同士による殺人事件、思いがけない別の先住民との出会いと交流、…、先住民を取り巻く厳しい現実と正面から向き合ったドキュメンタリーのはずです。著者はテレビ局のディレクターです。
ところが、イネ族の間で伝承されている韻文的な説話が随所に挿入されています。「森は川に囲まれている。…川は太く、深く、速い。川が行き止まりだ」だから、イネ族は森から出られないというのです。「私はあの音だけを恐れる。…森にはない音がすると…わたしは森を逃げる」。100年以上も前、ゴムの木を追って森に侵入してきた文明人が放つ鉄砲の音に怯えた様子が語られます。赤い実や、黒い実で化粧する理由も綴られています。さらに、若きイネ族の村長、ロメウの視線が絡んできます。
真実に迫ろうとする、幾重にも錯綜する虚実の仕掛けが秀逸です。未開のジャングル、先住民、文明、そしてドキュメンタリー…に対する私たちの思い込みが一枚剥がされる毎に、新しい物語が浮かび上がってきます。削ぎ落し、研ぎ澄まされた文体と内容、文学的センスに溢れた作品です。僅差で、授賞に及びませんでした。
『十五の夏』の著者は、紆余曲折を経て、外交、政治、さらに神学へと独自の視点から旺盛な研究、評論、執筆活動をつづける異能の作家です。
本書は、1975年、浦和高校に入学した15才の夏、著者がたった一人で冷戦時代のソ連、東欧を旅した42日間の記録です。上下2巻870ページに及ぶ大著ですが、筆者ならではの筆力と、少年の眼と感性を巧みに織り込んだ素朴な味わいが漂う作品に仕上がっており、一気に読み通すことができます。
少年は48万円もの経費を負担してもらい、「両親に申し訳ないと思ったが、好奇心が優先」したのです。その準備は周到で、15才とは思えない読書量、理解力、行動力、現地で出会った人々との会話力は、今の著者を彷彿とさせます。また、同時代のソ連をよく知る選考委員の一人によれば、著者の描写は正確だという。初めての、それも国家体制の異なる国々で、見るもの聞くものすべてを、乾いた砂が水を吸うように書き取ったメモは詳細かつ膨大だったと思われます。
しかし、本書は、少年の無垢な旅行記ではありません。40年の時空を経て、成熟した大人の視点を介した「人間発見」物語でもあるのです。その手法は見事というほかなく、「第8回梅棹賞」に決まりました。
信濃毎日新聞記事
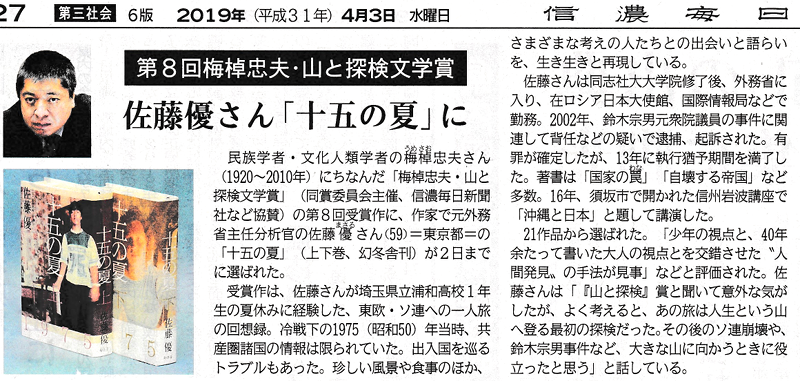
2011-2026 © 「梅棹忠夫・山と探検文学賞」委員会