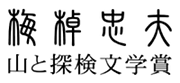著者 船尾 修(ふなお おさむ)
選考委員会の講評
「第13回梅棹忠夫・山と探検文学賞」の最終選考に残った5作品は以下の通りです。
- 山崎佳代子 ドナウ、小さな水の旅 ベオグラード発 左右社
- 岩崎 圭一 無一文「人力」世界一周の旅 幻冬舎
- 小坂 洋右 アイヌの時空を旅する〔奪われぬ魂〕 藤原書店
- 高田 晃太郎 ロバのスーコと旅をする 河出書房新社
- 船尾 修 大インダス世界への旅;チベット、インド、パキスタン、アフガニスタンを貫く大河流域を歩く 彩流社
選考対象作品は78本。今回ほど選考対象作品を楽しみながら読んだことはありませんでした。と同時に、最終選考作品5本に絞り込む作業はこれまでになく辛い時間でした。
その理由は5点満点で、4.5点前後の作品が多く、Aを残せばB、Cを落とせない、逆にAを落とせばB、Cも選外にせざるを得ない、というジレンマに陥ったからです。 そこで、2つの基準を設けて最終選考作品を選定しました。何より弊賞は「文学賞」です。ある特定の読者を対象にした(と思われる)論文調の作品は内容の如何を問わず除外しました。 次に、弊賞は自然界をフィールドにした「山と探検」を主題にしています。その原点を熟考しました。それでも甲乙つけがたい数冊から最後の1冊を選ぶ作業は悩ましく、文学賞を運営する怖さを改めて思い知りました。
はたして、選考委員も、5作品は一定以上の水準にはあるが、他を圧倒する評価を下せない状態に戸惑っているようでした。 選考委員は、それぞれが推す作品を取り下げようとする様子もなく膠着した議論がつづきました。2時間余の議論を経て、最後に『アイヌの時空を旅する』と『大インダス世界への旅』に絞られ、後者に決定しました。
ところで、5作品中3人の著者は北海道大学卒、そのうち2人は北海道新聞に勤務していました。「青年よ大志を抱け」の伝統は未だ途切れていないようです。 講評は以下の通りです。
『ドナウ、小さな水の旅』の著者は、セルビアの首都ベオグラード在住40余年の詩人で、日本と行き来をしながら旺盛な詩作、文筆活動を続けています。本書はドナウ川とその支流の町や村に出かけ、長い異国での暮らしのなかで緩やかに紡がれた人たちの交流を静謐な文体で描いた個人史で、紀行文です。
しかし、バルカン半島は「世界の弾薬庫」といわれている地域です。「ドナウ河の夏は眩しい。…水着姿の人々が小石を敷きつめ岸辺に寝そべる。鴎が空を舞い、水を船が過ぎていく。…ドナウの流れは、強く速く冷たい」。著者の詩情に心を寄せていると、その数行先には、ナチスによる「ドナウ河の氷の穴に入りきれなかった」ほどの大量虐殺があり、九死に一生を得ても、「アウシュビッツに連行され、還らぬ人になった」という惨劇が、冷静な筆致でつづられています。22編の「小さな水の旅」は、ドナウ流域の歴史の地層、ドナウの河底に沈潜している民族、王国、帝国の盛衰を読み解きつつ、「人類の残虐性」と対峙する旅でもあったのです。
重い対象に詩的で、繊細、控えめな文体で綴った好著ではありますが、この旅は著者にとっては「日常」の延長にあり、探検記と評価するのは難しく、授賞に至りませんでした。なお、旅先の地図を載せないのは、言葉の力を確信している著者の意図と推察しますが、日本の読者に馴染みが薄く、所在地すら分からない町や村、河川が大半で、適切な地図は必要ではないかという意見が全選考委員から出されたことを付しておきます。
『ロバのスーコと旅をする』は、2022年から1年間のイラン、トルコ、モロッコを巡る「ロバとのあてのない放浪の」旅行記です。著者とロバとの自由で気ままな触れ合いと、ゆったりした旅と協奏するシンプルで衒いのない文章のリズム感が、独特な魅力を醸し出しています。
徒歩の他に自転車、リヤカー、カヌーなど無機質な移動手段を伴った旅は無数にあります。著者も、学生時代は国内のヒッチハイクに明け暮れていました。2011年、新聞社を辞してから2年以上もかけて、バスで南米大陸、スペイン・サンチャゴ巡礼の道800キロ、その終着からリスボンまでは徒歩で、2016年、自転車でモロッコへ移動、ここでロバと出会い1500キロを歩き続けました。
道具に対しても、長年利用していれば様々な感慨が湧きますが、一方通行的な思い入れです。しかし、6000年ほど前から家畜化されたロバとの相互交流は可能でしょう。例えば、こんな場面です。著者は転んだまま動かないスーコを見て、「今日はもう歩かなくていいと思っている」と推測します。意外とずる賢い奴と思いながら「尻を軽く棒で叩くと、スーコは悪びれる様子もなく、のっそりと歩き始めた」。愛玩用ではない動物との接触がほとんど無くなった私たちには、著者とロバとの触れあいは新鮮で魅惑的でした。
著者はX(旧ツィッター)で発信し、フォロワーは10万人を超えています。素朴さと最先端の文明の利器が交錯する興味深い旅行記です。しかし、ロバの存在が当たり前の国々では、ロバとの旅が引き起こすだろう様々な出来事が、予想される範囲をいささかも出ていないと。授賞には届きませんでした。
誰もがする「旅」に、独自のルールを課すことで「冒険」性を帯びてきます。著者の場合は「無一文、人力、野宿・世界一周」です。このルールを厳格に守るほど、人々の注目を集めるようになります。
『無一文「人力」世界一周の旅』の著者が、01年3月14日、前橋の実家を出たときの所持金は160円。徒歩、ヒッチハイク、野宿(時折、友人宅等などに居候)をしながら、日本一周後、中国青島から、アジア全域、中近東、ヨーロッパ諸国を周遊、24年3月現在、一度も帰国せずに、南米大陸を自転車で移動中だそうです。
その間、2005年6月、公募登山でエベレスト登頂、手漕ぎボートで、05年11月、ガンジス河1600キロ、カスピ海横断、23年1月ポルトガルから106日かけて大西洋を横断。著者の旅は、間違いなく大「冒険」です。しかし、著者は、友人たちにエベレスト登頂の資金を呼びかけ、街頭で手品を演じながら小銭を得て、スポンサーから大西洋横断の資金を獲得します。決して「無一文」ではないのです。時にフェリーもバスも使い、友人、知人宅に居候し、安宿も利用します。プリミティブな「冒険」のようですが、情報収集、協力者への呼びかけなどに、現代文明の利器を使いこなしています。
著者には、壮大な時空を行き交う野性味と、ルールに対する柔軟な対応力が内在しています。後者の姿が気になり、これまでの多くの冒険者が行ってきた「旅」を凌駕するまでに至ってないという評価があり、授賞を逸しました。
『アイヌの時空を旅する』の著者は、札幌市生まれ、北海道大学を卒業し、北海道新聞に奉職、論説委員、編集委員を務めた方であり、アイヌに関わる著作も多数あります。「アイヌ民族と和人が複雑にかかわり合い…織りなしてきた北海道」の「歴史」を学術的にも、肌感覚としても確かな認識があります。それを前提に、著者は脈々と受け継がれてきたアイヌの文化や歴史、苦悩を体感し、「アイヌ側からの視点を取り込んだ新たな歴史観を構築」しようと、「現場」に出かけます。本書はその集大成です。
とりわけ、アイヌ民族最後の大決起「クナシリ・メナシの戦い」(1789年)の現場を巡る著者の体験は鮮烈です。標津町市街地から最北の蜂起集落・羅臼町海岸町まで、点在する集落を歩き通します。そこで、アイヌの「言葉も文化も儀式も根こそぎ奪われた」はずの悲惨な蜂起の様子が、脈々と伝承されていた事実を知ります。「闘う人、まつろわぬ人があの時代にも、この時代にもいたーその記憶の蓄積が、次の時代の担い手にさらなる一歩を踏み出させる力に」なり、それゆえに「人間の国土や集落は、たとえどれほど荒廃したとしても自律的に再生力を持っている」。著書が肌感覚の旅を介して得た確信です。
本書は、目的が明白で、学術的に吟味され、構想力に長けた好著です。ただ、カヌー、カヤック、山スキーによる追体験の旅は、著者がこれまで積み重ねてきた研究成果の再確認、補強という意味合いが感じられ、新たな発見が、いま一つ不明という意見が出され、僅差で授賞を逃しました。
『大インダス世界への旅』は、3000キロに及ぶインダス河流域を30年近い年月をかけて通い続け、圧倒的な大自然の描写、自然に寄り添い、翻弄され、時に民族的、歴史的、政治的な争いに巻き込まれながら暮らす人々の様子を活写した民族誌的大著です。
本書は、インダス河の最奥地、チベット高原西部に位置し、五体投地で知られたチベット仏教の聖山、カン・リンポチェ(カイラス)から始まります。土着信仰に代わる「新しいカミ、仏教」の魅力を伝える仮面舞儀礼が伝わるラダック、真冬のわずかな期間だけ姿を現すザンスカールの「氷の回廊」の遡上、インド・パキスタンの間で紛争の絶えないカシミール……、そして最終章の「インダスの残り香をかぐ」モエンジョダロで終わります。それは「民族や文化や歴史や自然のなかを行ったり来たりしつつ、ときには時空を越えて妄想を膨らませたりしながら」続けた旅でした。
それを可能にしたのが、岩壁に張り付き頂を目指す登山家の挑戦心、自然・人・社会の在りようを一瞬で切り取る写真家の感性、多様な事象を文章で伝える文筆家の創造力。これらの能力が程よい均衡を保ち、著者は、対象としての地域の姿を描き出すことに成功しています。
本書は、簡単にはまとめきれない「インダス世界」に挑んだ冒険精神に溢れた作品であり、第13回梅棹賞に決定いたしました。ただ、「河」が描き切れてない、尻すぼみになっている、各章毎に理解を深める手助けになるような地図があれば、本書の完成度はさらに高まったのではと、指摘する選考委員がおられました。
信濃毎日新聞記事

2011-2025 © 「梅棹忠夫・山と探検文学賞」委員会