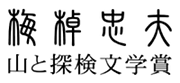著者 中村逸郎(なかむら いつろう)
筑波大学教授
1956年島根県生まれ
学習院大学法学部政治学科卒業
モスクワ国立大学留学
選考委員会の講評
「第6回梅棹忠夫・山と探検文学賞」の選考委員会は2月28日、山と溪谷社会議室において、選考委員5人全員が出席して行なわれました。今回は選考対象43作品から、最終選考に残ったのは次の6作品です。
- 宮城公博著『外道クライマー』(集英社)
- 片野ゆか著『動物翻訳家』(集英社)
- 高橋大輔著『漂流の島』(草思社)
- 植竹 惇著『雪と氷の世界を旅して:氷河の微生物から環境変動を探る』(東海大学出版部)
- 村上大輔著『チベット 聖地の路地裏 : 八年のラサ滞在記』(法蔵館)
- 中村逸郎著『シベリア最深紀行:知られざる大地の七つの旅』(岩波書店)
毎回、「梅棹忠夫」との相関性、「山と探検」の先駆性、独創性、「文学」としての完成度などを巡って議論が白熱します。選考委員諸氏は「梅棹忠夫」、「山と探検」、「文学賞」の記号価値を反芻し、軸足を微妙に変えながら、ようやく「一冊」を選び出すのです。今回も激戦でした。
『外道クライマー』は、文章力、意表を突く構成、個性豊かな行動力に引き込まれ、一気に読むことができました。著者は「偏屈な社会不適合者」を自認する「沢ヤ」です。同時に、沢登りの「価値観の根底には、日本古来から続く沢を中心とした里山での生活が存在している」という、「外道」とは対極の真摯な認識があります。このアンビバレンスが本書の魅力の源泉です。沢登りは著者の内面からほとばしる表現であり、パフォーミングアートなのです。しかし、最終章で明かされた那智の滝登攀の動機などの記述に違和感が残りました。さらに今回、これまでの授賞作品と同系統の本書を選ぶと、「梅棹忠夫」の多様性、すそ野の広さに適うのだろうかという懸念が生じました。苦渋の思いで授賞を見送りました。
『動物翻訳家』は、全国4カ所の動物園で飼われている4種類の動物と飼育員との、一筋縄ではいかない交流を取材したものです。著者の温かで、好奇心に富んだ人柄が滲み出るような文章で、知っていそうで実はそうではない「動物園」の姿が明かされ、ページをめくるのが楽しくなります。「動物園」という様々な制約のなかで、展示物として飼われている動物に対し、飼育員は「使えるかぎりの能力と感覚を総動員」して、動物たちの「気持ちや本音を理解」し、動物本来の行動や生態を引き出そうとします。しかし「言葉」が介在しない人と動物との間で本当に理解しあえるのか、結論の出しようがない未知の領域への航海なのです。これを「探検」といえるのか、選考委員の「常識」は覆りませんでした。
『漂流の島』は、鳥島に漂着した人たちを追った力作です。漂流者たちに寄り添う著者の心根が醸し出す筆力、歴史・文学的資料を駆使しての展開には説得力があります。しかし、何か腑に落ちないのです。鳥島は、明治期から気象観測所が閉鎖される昭和44年まで、多くの人々が暮らしていました。現在は定期的に「アホウドリの生態調査」が行なわれています。鳥島は未知でも、未踏の場でもないのです。探検家として「物語を旅する」著者ならではの、例えば、漂流にいたる航海、孤島での生活などの追体験に挑んでいたなら、という思いに駆られたのです。7日間の滞在で2カ所の洞窟を調査しますが、漂流者が生活した痕跡は確認できませんでした。鳥島の調査制限が廃止され時、著者には誰もが納得する成果を出せる力量があるはずです。授賞には届きませんでしたが、その時が楽しみです。
『雪と氷の世界を旅して』は、時に氷点下数十度になる極地、高地の氷河、氷床に生息している「雪氷生物」を追い求めた研究・紀行です。その採集地は南米パタゴニア、アルタイ山脈、アラスカ、中国祁連山脈、グリーンランド、ウガンダ・ルウェンゾリ山などで、凡人には想像を超えた過酷な自然環境です。著者は、氷河、高山で安全に活動するための登山、スキー、犬ぞりなどの技術、現地の食生活にも馴染むなど、研究以前の習得にも力を注ぎ、未知の世界に挑む気概にも共感できます。しかし、著者がどのような読者を想定しているのか明確でないために、微生物の生態、探検・冒険紀行、自然・環境問題など、すべての分野で物足りなさを感じてしまいます。「雪氷生物採取・探検紀行」という新たな分野の確立を願っています。
『チベット 聖地の路地裏』は、ラサ滞在8年間に及ぶ著者のフィールドワークをまとめたものですが、観察者の専門領域に偏ったものではありません。友人のラブレター、相手の慈悲にすがりながらの交渉術、死や生(性)を笑い飛ばすセンス、市井に溶け込んだシャーマン、聖地巡礼は老後の一大イベントなど、チベット人の神仏と生きる「路地裏」の暮らしぶりを、豊富な写真と平易な文章で綴っています。確かで公平な異文化への眼差しにも好感が持てます。ただ、8年のチベット滞在が却って「日常と非日常」、「生活者と観察者」の緊張(境界)をあいまにしたように思えます。例えば、青蔵鉄道の全通が及ぼした影響、決して裕福ではない市民がどのように寺院や僧侶を支えているのか、異国の基底にある経済、政治、文化を掘り下げて語る視点がほとんどありません。慣れが、そうさせたのでしょうか。僅差で受賞を逃しました。
『シベリア最深紀行』。魅力的なタイトルです。シベリアという広大、過酷な大自然のなかで、わずか数十人、数百人の村、数百キロの大地を移動する遊牧民の暮らしとシャーマンの活躍、そして彼らを取り巻く国家、民族、言語、宗教との関わり。どれも今日的で、微妙で、興味の尽きないテーマが取り上げられています。また、最近のアメリカ、ヨーロッパ、そして我が国の政治・社会情況を思う時、本書の情報は重く、貴重です。著者はロシア語が堪能で、80年代から90年初頭までモスクワ大学、ソ連科学アカデミーに留学、その後も頻繁にロシア(ソ連)に出かけています。本書は、シベリアの状況を十分に吟味した、いぶし銀のようなエッセンスが散りばめられています。しかし、本文が200ページ、一つのテーマについて地元民1人、2人のインタビューを紹介しながら、30ページほどなのです。納得ゆくまで書き込んで欲しかったという不満はありますが、本書で終わらないはず、という確信と期待を込めて、選考委員一致で授賞が決まりました。
信濃毎日新聞記事

2011-2024 © 「梅棹忠夫・山と探検文学賞」委員会