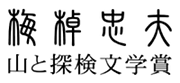山と溪谷社 編
選考委員会の講評
「第12回梅棹忠夫・山と探検文学賞」の選考会は3月7日、山と溪谷社会議室において、選考委員全員が出席して行なわれました。最終選考に残った4作品は以下の通りです。
- 堀田絵里 1961 アメリカと見た夢 岩波書店
- 中村 寛 アメリカの〈周縁〉をあるく: 旅する人類学 平凡社
- 奈倉有里 夕暮れに夜明けの歌を 文学を探しにロシアに行く イースト・プレス
- 山と渓谷社編 日本人とエベレスト ―植村直己から栗城史多まで 山と渓谷社
今回の選考対象作品は84点。第1回の91点以来の作品数であったが、事務局としては手放し喜べないというのが本音です。弊賞の制定時に意図した「山岳・探検」をテーマにした「本流」の作品が、回を重ねるごとに減少しているからです。 最近の6年間をみても、最終選考に残った作品は10点ほどで、受賞作品は『考える脚』のみです。
今年こそ、一点でも多く「本流」を見つけ出したいと思うあまり、全方位的な思考と行動力で、既成の概念や領域にとらわれない「梅棹忠夫」流の表層をなぞり、探検の概念や作品の選定領域を広げ過ぎたのでは、という忸怩たる思いが消えません。 今年の最終選考作品は、例年より少ない4作品になったのには、以上のような状況が影響しています。
最終選考に残った4作品は対象に向かう明確な視点、切り口の斬新さで、著者(編者)の感性、生き様が活きいきと浮かび上がり、読み応えがあったという評価で選考委員は一致していました。 とりわけ、『日本人とエベレスト』は時々の社会的変遷、登山隊の人間関係などを織り込み、「日本人」とエベレストの関わりを活写、従来型の四角四面の「山岳通史」とは一線を画しています、 新たな地平を切り開いた作品と評価され、全委員一致で授賞が決まりました。
なお、今回の選考方法について申し添えておきます。
今回、『日本人とエベレスト』の編集、執筆で、選考委員の江本嘉伸氏、神長幹雄氏が中心的な役割を果たしており、その取扱いが問題になりました。
選考会議の始めに、全委員と事務局で協議し、江本氏、神長氏は会議への出席を見合わせてもらうことにしました。選考会議は3人の選考委員でおこない、2氏は選考過程でいささかも関与することはありませんでした。講評は以下の通りです。
『1961年 アメリカと見た夢』の著者はアメリカ在住の歴史研究者で、日本語による初のエッセイです。 2021年3月からコロナ禍のため、全米各地でロックダウンが始まりました。 鬱々とした日々のなかで起こったマイノリティーへの差別と攻撃、それに対する抗議行動、敗北を認めないトランプ大統領、トランプ支持派による連邦議会へ乱入等々。それらの行動のいずれもが「自由」と「権利」を標榜します。
否定のしようもないアメリカの落日。「まぶしいアメリカの残光」に「十分触れてきた」と自認する著者は、日本人、そしてアメリカ人にとっての「アメリカ」を問いかけます。 その手掛かりが、1961年にグレイハウンドバスで、アメリカ大陸を往復した著者の父親を含む4人の日本人大学生と、その日記でした。 ケネディに象徴される「アメリカブランドの絶頂期」と、今のアメリカとの間を自在にワープしながら、アメリカの多面的な姿を描き出します。
長いアメリカ生活で身についた肌感覚と、研究者の眼差しで「アメリカ」に迫る手法は刺激的で、的確な表現力が一層効果を上げています。 しかし、コロナ禍とはいえ、本書は青年たちの旅路を実際に追体験した著者の行動譚ではなく、その意味で授賞に至りませんでした。
『アメリカの〈周縁〉をあるく 旅する人類学』は人類学者とニューヨークを拠点に活躍する写真家との共著です。12年夏、ニューメキシコ州アルバカーキを皮切りに、2018年秋、ミズーリ州セントルイスで終わる。旅は毎年1回、1、2週間ほどの日程で、2人は、行き当たりばったりの人と風景の出会いを楽しみながら「アメリカの周縁」を訪ね歩いていく。
しかし、彼らの関心は明確です。「飛び切りのホスピタリティを発揮する」が「深い悲しみも知っている」人と、「生業や生活を営む身体と、利害や信仰を説明し弁明する言語」との深い乖離に翻弄される人たちとの、「見入れば魅入られて、ねじ伏せられ、吸い込まれてゆきそう」な圧倒的な風景との出会いです。2人の感性が響振しあいながら人、土地、歴史、文化が描かれ、「アメリカをつくっている」民衆の素顔が浮かび上がってきます。だが、標題に「人類学」と明記する以上、複雑で矛盾に満ちた〈周縁〉を執拗に追究し、つかみ取る強靭さが欲しいという意見があり、授賞には至りませんでした。
『夕暮れに夜明けの歌を』は隠喩性に満ち、含蓄に富んだ標題です。著者は、語学好きの母親に煽られるように、高校1年生の時に「なんとなくロシア語」に手を出します。手当たり次第に教材を手に入れ、ロシア語学習にのめり込みます。その当然の帰結としてロシア留学の思いが募ります。
2002年からペテルブルグ大学語学学校、モスクワ大学予備学科を経て国立ゴーリキー文学大学に入学し、日本人初の卒業生(2008年)となります。しかし、本書は単純な留学記ではない。著者は「人と人との文脈」をつなぎ、「記号から思考へと続く光」である文字、言葉、文学を追求したのです。それは、第1章の末尾に暗示されています。「目の前には…言葉の森がある。坂道の向こうの図書館から漏れている―あれは本の光だ」と。
本書は、個人的、社会的、政治的事件事象の闇と光を見据え、文字、言葉、文学を介して「人間」を深く理解しようとする詩的で、知的な労作です。ただ、梅棹賞の求める「山と探検」から最も離れているという指摘があり、僅差で授賞を逃しました。
『日本人とエベレスト』は1970年5月21日、2人の日本人登山家、松浦輝夫と植村直己によるエベレスト初登頂50年を契機に編まれた作品です(出版は2022年)。本書は、当事者ではない山岳関係の編集者、ジャーナリスト、ライター等5人がそれぞれの視点から、人類にとってのエベレストの「聖性」と、それが失われていく過程を客観的、冷静、かつ生々しく追った作品です。
世界の登山家たちが国家の名誉を賭けて初登頂を競っていた50年代の「黄金期」、そしてその後の70年代から90年代前半までの女性、厳冬期、より困難なルート、無酸素など、厳しい条件下で挑むバリエーション時代(鉄の時代)。未だ「聖性」のベールに包まれたエベレストに挑む日本の精鋭登山家たちの迫力、緊迫感がしっかり伝わってきます。
だが、90年後半から、その「聖性」に陰りが生じます。登山の大衆化、地球環境への意識の高まり、SNSなどの広がりなどを背景に、徐々に増えだした公募登山、野口健(けん)らによるエベレスト清掃隊の活動、さらには栗城史多(のぶかず)の劇場型登山です。
標題の「日本人」は一部の精鋭登山家だけでなく、ちょっとした切っ掛けで、登頂者にも熱烈な支援者にもなり得る市井の日本人も含まれていることに、読者は気づかされます。「エベレスト」と、時々の時代情況、人の在りようとの一筋縄ではいかない関係にも目配りが効いた好著であり、選考委員の全員一致で第12回の梅棹賞に決定しました。
信濃毎日新聞記事

2011-2025 © 「梅棹忠夫・山と探検文学賞」委員会