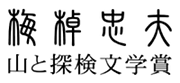著者 小野 和子(おの かずこ)
みやぎ民話の会顧問
1934年、岐阜県高山市に生まれる。
東京女子大学日本文学科卒業。
1975年に「みやぎ民話の会」を設立し、現在は同会顧問。
編著書に『長者原老媼夜話』(評論社1992年)『みちのく民話まんだら』(北燈社1999年)『七ツ森周辺の民話』(日本民話の会2007年)などがある。
選考委員会の講評
「第10回梅棹忠夫・山と探検文学賞」の選考会は3月22日、山と溪谷社会議室において、選考委員全員が出席して行なわれました。選考対象43作品から、最終選考に残った5作品は以下の通りです。
- 伊藤精一『俺のアラスカ 伝説の“日本人トラッパー”が語る狩猟生活』(作品社)
- 髙橋大輔『剱岳 線の記 平安時代の初登頂ミステリーに挑む』(朝日新聞出版)
- 遠藤ケイ『蓼食う人々』(山と渓谷社)
- 鹿野勝彦『ヒマラヤ縦走 「鉄の時代」のヒマラヤ登山』(本の泉社)
- 小野和子『あいたくて ききたくて 旅にでる』(PUMPQUAKES)
果てないコロナとの格闘のさなか、第10回梅棹賞の選考対象作品の選定が始まりました。すぐに、これもコロナの影響なのかと戸惑いを覚えたのです。これまでになく、山、探検、冒険を扱ったオーソドックスな作品が非常に少ないのです。実はこの状況が、選定作業に影響を及ぼしたのです。
第1次選定作業で43作品を選び、第2次で16作品に絞りました。が、いま一つ確信が持てないのです。例年に近い作品数は選びたいと、「山」「探検」の概念を拡張しすぎたのでは、という不安が過るからです。迷ったら原点に戻る、何度も「梅棹忠夫」に立ち返りました。「自分の足で歩いて、自分の目で見て、自分の頭で考える」、「思いつきこそ独創、思いつきがないものは、ひとのまね」という姿勢です。
最終選考に残った5本は、プロパーにありがちな「伝統」、「正統」という呪縛に囚われず、独自の視点で対象を追いつづけた個性的な作品です。しかし、選考会議では速やかに、全員一致で『あいたくて ききたくて 旅にでる』(PUMPQUAKES)に決まりました。「何度も目頭を熱くした作品、このような書き手がいたのかという驚き」、「村・人に飛び込む著者のおののきがリアルに伝わってくる」、「SNS時代に一石を投じた作品」、「自己と他者との抑制された距離感が生んだ文章が読ませる」。選考委員全員が圧倒されたのです。
『俺のアラスカ 伝説の“日本人トラッパー“が語る狩猟生活』を一読、これほど破天荒な日本人がいたのかと畏怖の念を覚えます。本書は、録音された伊藤氏の語りをもとに、元妻が編集した「聞き語り」形式の作品です。1940年、東京都府中市に生まれた伊藤氏は、73年、アラスカに移住します。偶然知り合った現地人から罠猟を習い、 数年で現地の猟師たちも一目置くほどに成長し、アラスカの大地を縦横無尽に駆け巡っていました。でも、単なる冒険譚ではありません。文明社会のカプセルに守られている私たちには想像を超えた極寒の大自然、野生動物との壮絶な関わり、現地人の開拓者魂に溢れた暮らし振りが生き生きと語られています。「たった一人での猟暮らし、何十年やってもなれというものは一切ない、自然は恐ろしい」という著者の言葉が胸に刺さります。しかし、本書からは時に対峙しつつ語り手の「本音」「真実」に迫ろうとする書き手、聞き手の緊張感が伝わってきません。かつて生活を共にした「著者自身の体験、思いが都合よく隠されている」のでは、という思いが払拭できませんでした。
『剱岳 線の記 平安時代の初登頂ミステリーに挑む』は、探検家としての高橋大輔氏の嗅覚が捉えた、剱岳初登頂者の謎に挑む意欲作です。著者も指摘しているように、剣岳は立山信仰のご神体として遥拝する山であって、登ることが許されていませんでした。しかし、1907(明治30)年7月、陸軍参謀本部陸地測量部隊が頂上で発見したのは、錆び付いた銅製の錫杖頭と鉄剣でした。鑑定の結果、奈良時代後期から平安時代初期のものとされました。歴史の闇に埋もれた剱岳初登頂は誰で何時なのか、何のための奉納なのか、著者は謎ときに突き進むのです。その精力的な活動の一々については記しませんが、山岳信仰について、荘園とのつながりから解明する手法は独創的で、新たな地平を切り開いたものと、高く評価できます。また、結論に向かって読者をひきつけていく筆力も見事です。しかし、初登頂者の登山ルート選定、ハゲマンザイと万歳氏とのかかわり、初登頂時期が二転三転する論証など、結論にいたる過程がやや独断的で、強引すぎたように思えます。またも授賞には届きませんでした。
『蓼食う人々』の著者は「草の根民俗学」を志向し、「自分の足で旅をし、自分の目で見、手で触れられるもの以外は書かないという実践主義を堅持」している作家、イラストレーターです。本書で紹介されている「蓼」は野兎、鴉、トウゴロウ、岩茸、野鴨、鮎、鰍、山椒魚、スギゴケ、スガレ、ザザ虫、イナゴ、槌鯨、熊、海蛇、海馬です。ゲテモノと思われるもの、未知の食材もありますが、読者によっては当たり前に食しているもの、懐かしいものもあります。しかし、著者がこれらの食材を口にするまでの方法を知ると、並みのアウトドア派、自然愛好者には及びもつかない体験の深さに驚愕させられます。全国を巡り、当代きっての猟師、釣り師たちと一緒に捕獲、採集にかかわるのです。読者は食材の調理法や味以上に、熊や野兎を追うマタギ、遊び心に溢れる鴉の捕獲やスガレ追い、緊張感に富んだ闇夜の海蛇捕りに引き込まれます。しかし、採集者、捕獲・採集地は明確なのですが、時期がまったく記載されていません。ドキュメンタリーとして致命的という指摘があり、授賞には届きませんでした。
『ヒマラヤ縦走』の著者は、文化人類学者としてリトルワールド研究員、金沢大学教授、同副学長を歴任された異色の登山家です。本書は著者23歳の時に初めて遠征したキンヤンキッシュから、42歳でのカンチェンジュンガ縦走まで、6回の遠征を報告書の体裁でまとめた回想録ですが、著者自身と著者とかかわった人々、日本山岳界へのレクイエムのような作品です。半世紀余を経たからこそ見えてきた、それぞれの時代状況、登山様式や技術の変遷、登山隊の特性、組織、人間関係などについて、研究者らしい目配りと記録をもとに冷静、客観的、かつ敬愛の念を込めて論じています。エベレスト隊などの苦い経験から、著者が隊長を務めたナンダデヴィ縦走では、準備期間中に時間をかけて全員が納得するまで計画を協議し、隊員それぞれの役割、意識の共有を図ります。遠征終了後も次の計画を話し合うほどの絆で結ばれた由縁です。上質な文章で、山に無縁な人にも興味深い内容となっています。しかし、新たな発見、探検というには少し弱く、また、会心の遠征だった「ナンダデヴィ縦走」を核に、6編にメリハリをつけた編集でもよかったとの意見もあり、授賞を逃しました。
『あいたくて ききたくて 旅にでる』は、今年87歳になられる小野和子氏の50年にわたる民話採集の道程を綴った作品です。結婚を機に仙台に移住、35歳の時に何かに突き動かされたかのように、民話を求めて宮城県中を巡りつづけます。列車やバスを乗り継ぎ、1時間でも2時間でも歩いて村中を一軒、また一軒と訪ねるのです。人の気配さえ感じられない家、人がいても取り付く島もなく追われます。ようやく、「乞食が施しを得た」ように民話を聞かせてくれる村人に出会うのです。本書には35編の再話作品が掲載され、そのすべてに採集をした地域、時期、語り手の名前と生年月日が明示されています。忘れ去られたかのような村の時空感を全身全霊で捉え、語り手の来し方に思いを馳せた証なのです。著者の内省力に支えられた地道でぶれない思考、しなやかな感性と優しいまなざしが、民族社会で生きる村人たちの「血の吹き上がる現実」、時に残酷な社会の仕組みを剥き出します。民話は生活のリアリティから生まれ、語り手の生きざまが投影されていると、読者は気づかされます。梅棹賞創設10年の節目に相応しい凄い作家、作品に出合いました。
信濃毎日新聞記事

2011-2025 © 「梅棹忠夫・山と探検文学賞」委員会