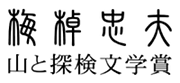著者 川瀬 慈(かわせ いつし)
1977年岐阜県生まれ。
国立民族学博物館/総合研究大学院大学准教授。
専門は映像人類学、民族誌映画。アフリカ、主にエチオピア北部の地域社会で活動を行う吟遊詩人、楽師たちの人類学研究を行っている。同時に人類学、シネマ、現代アートの実践の交差点から、イメージや音を用いた話法を探究する。
選考委員会の講評
「第11回梅棹忠夫・山と探検文学賞」の選考会は3月7日、山と溪谷社会議室において、選考委員全員が出席して行なわれました。最終選考に残った5作品は以下の通りです。
- 三浦 英之『災害特派員』(朝日新聞出版)
- 国分 拓『ガリンペイロ』(新潮社)
- 田島木綿子〚海獣学者、クジラを解剖する~海の哺乳類の死体が教えてくれること』(山と溪谷社)
- 小松 由佳『人間の土地へ』(集英社インターナショナル)
- 川瀬 慈『エチオピア高原の吟遊詩人~うたに生きる者たち~』(音楽之友社)
今回の選考対象作品は71点、質、量とも盛況であった。著者の年齢も30代から80代と幅広く、女性が14名というのも初めてのことです。著者たちが活動するフィールドは多彩で、その分野は民俗学、民族学、人類学、歴史、音楽、精霊信仰、民話、動物、化石、紛争、災害・・・等、多岐にわたっています。作品の形式も回想録、自伝、伝記、紀行、論文、小説風、写真文一体型など様々で、作品を手にするのが楽しみでした。同時に、甲乙つけ難い作品が多く、5冊に絞る作業はこれまでになく苦痛でした。最後は好きか嫌いかで選び取った作品もあったことを正直に告白しておきます。
5作品、いずれも読み応えがあるという評価で、選考委員は一致しました。しかし、フィールドもジャンルもことなり、「探検」や「ドキュメンタリー」の概念に収まりきらない作品をどう評価し、選出するのか難しい判断を迫られました。果たして、選考会はこれまでになく紛糾し、結果が出るまで3時間余を要しました。
最初の投票では『災害特派員』と『人間の土地へ』に各2票、『エチオピア高原の吟遊詩人』に1票と分かれました。休憩を挟んで、さらに議論を進め、『エチオピア高原の吟遊詩人』が4票を獲得し、授賞が決まりました。講評は以下の通りです。
『災害特派員』は新聞記者の手記です。著者は「東日本大震災」(2011年3月11日)発生の翌日からほぼ1年間にわたり、現地の人と一緒に生活をしながら取材活動に携わりました。取材の拠点は、記者の初任地の仙台市に近く、土地勘もある南三陸町です。
人も、大地も、建造物も、すべてを破壊し流し去った傷跡が生々しい。被災者、取材者、それぞれが理性と感情のはざまで揺れ動き、時に心情をむき出しにしながら対峙し、認め合う。そんな被災地というフィールドで、旧知、あるいは取材が縁で交流を始めた10余人との濃密な交流を介して、巨大災害の悲惨さを浮かび上がらせていく手法が見事です。彼/彼女らそれぞれが背負った幾筋もの「物語」を交錯させながら描く筆力も圧倒的です。しかし、著者が強調するほどに、「全国紙の記者」という立ち位置から抜け出していないのではないか。また、コロンビア大学留学体験に章を割いて「ジャーナリズム」論を展開するのは、いささかペダンチックではないかという批判があり、授賞に至りませんでした。
『ガリンペイロ』の著者はテレビディレクターです。著者の主なフィールドはアマゾンの奥深い地域で、そこで暮らす少数民族に迫る手法は圧巻でした。その成果である『ヤノマミ』(第1回)、『ノモレ』(第8回)が最終選考まで残りました。今回も授賞に至りませんでしたが、その理由は最後に述べます。
アマゾン最奥の村から雨季で3~4日、乾季なら1週間ほどの船旅、さらに車で数時間ほどのところに、闇の金鉱山が点在している。ガリンペイロたちは、そこで黄金を掘る「ブラジル最底辺の男たち」のことである。彼らに課された、尋常ではない11か条の掟を知れば、納得できるだろう。曰く、前科の有無、犯罪歴も問われず、凶器を持つのも自由だが、金鉱の場所を明かしたときは死を覚悟すべき、というのだ。著者も例外ではない。人類学者でもあまり入りたいとは思わない、喧嘩や殺人が横行する、決してノーブルとは言えない集団世界を描き切る。その手法が、意識的にノンフィクションとフィクションの境界を曖昧にすることだったと思われます。が、その一点で、授賞を逸しました。
『海獣学者、クジラを解剖する』は、知っているようで知らない世界を、著者の熱気あふれる筆致で描いた、読みごたえのある作品です。著者は国立科学博物館に勤務する研究者です。学生時代にバンクーバーで出会った野生のシャチに魅せられ、海獣学者になる決心をします。以来、20年間で解剖した海獣は2000頭にも及ぶという。捕鯨が禁止されている現在、クジラの解剖は座礁したり、浜に打ち上げられたりした死体に限られます。このような現象を「ストランディング」というが、日本近海で年間300頭ほどにのぼるといいます。
ストランディングの連絡が入ると、著者は日本全国どこへでも駆け付けます。現場は、腐敗したクジラが発する「それはそれは恐ろしい強烈なニオイ」まみれ、血まみれ、汗まみれの修羅場です。本書には、その過酷な体験から導き出された未知の情報に溢れています。巨大クジラの解剖の手順はもとより、解剖後の処理の仕方、標本の作り方や管理の方法、海獣らの生態…。が、弊賞が想定している「探検」といえるのか疑義が多く出され、授賞を逃しました。
『人間の土地へ』の著者は現在40才。2006年、母校のK2(標高8611 m)遠征隊のアタック隊員として参加、その下山時の描写に心を揺さぶられる。標高8200m、酸素無しのビバーク。「息が苦しい。寒い。ハア、ハア、ハア。荒い息づかいが聞こえ目が覚めた。…隣に生きた人間がいることに…安堵感があった」というほどの極限の世界に身を曝したのです。この体験が本書のプロローグであり、書名の伏線になっています。著者は挑む場から、人が生業を営む場へと向かう。
2008年から中国、ユーラシア大陸を歩く。シリアの砂漠で遊牧民と出会い、その一族の青年と恋に落ちる。青年の家族、その周辺の人たちとの交流、宗教、言葉、内戦、女性の地位、難民…、様々な軋轢を乗り越えて2人は結婚。今は夫と子供と日本で暮らしています。その生き様は波乱に満ちているが、著者の歩みは、不思議なほど軽やかな印象を受けます。個の体験、身近で得た情報を普遍化する作業、その過程で生じる衝突、対立、葛藤、緊張にもう半歩でも切り込んでいたら、独創性に富んだ作品に仕上がったのではないか。次作に期待したいと思います。
『エチオピア高原の吟遊詩人』には見知らぬ言葉が溢れています。チュンブル、マシンコ、アズマリ、タカブ、ラリベラ、シュカッチ…、さらに隠語の解説まで。が、未知の扉を開くほんの少しの勇気と好奇心、既知の事柄を手掛かりにする機転があれば、異文化・社会が醸し出す豊穣の世界に浸ることができるのです。
著者は、2001年からエチオピア北部の古都ゴンダールを拠点に、弦楽器マシンコを弾き語るアズマリ、門付けを行うラリベラという吟遊詩人の集団に深く入り込みます。読み進むうちに彼らの立ち位置が、わが国の瞽女、角兵衛獅子、琵琶法師、ヨーロッパのロマ、ブラジルのレペンチスタなどと重なり、理解を助けています。著者の、初めての地、調査対象に分け入っていく力、方言、隠語まで取得する言語能力、言葉の壁を越えて「音楽」や「文学」を伝える感性は見事で、人類学的探検の魅力をよく伝えています。文学作品としての完成度も高く、第11回の梅棹賞に決定いたしました。ただ、静止した写真を何枚載せても、彼らのリズム感は伝わりにくく,キャプションを末尾に一括しているのも煩わしいという指摘もありました。
信濃毎日新聞記事

2011-2025 © 「梅棹忠夫・山と探検文学賞」委員会